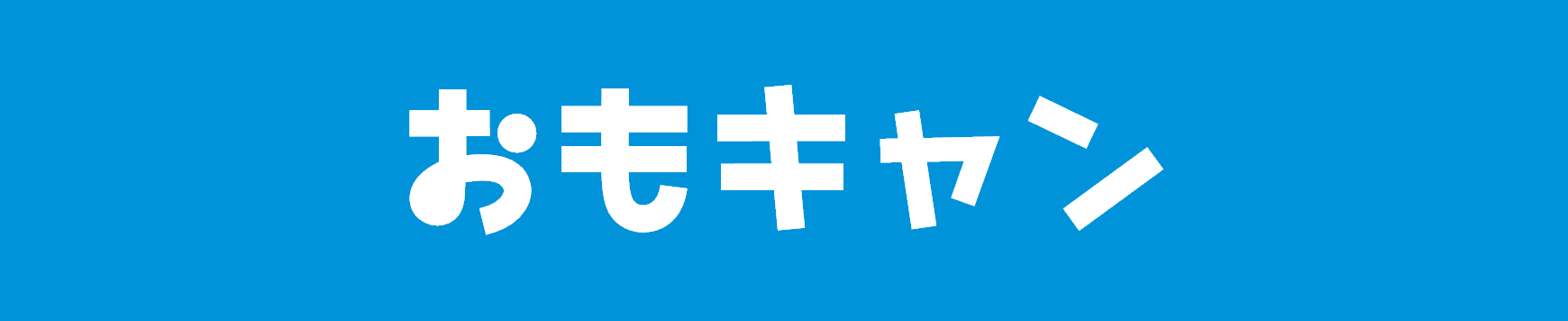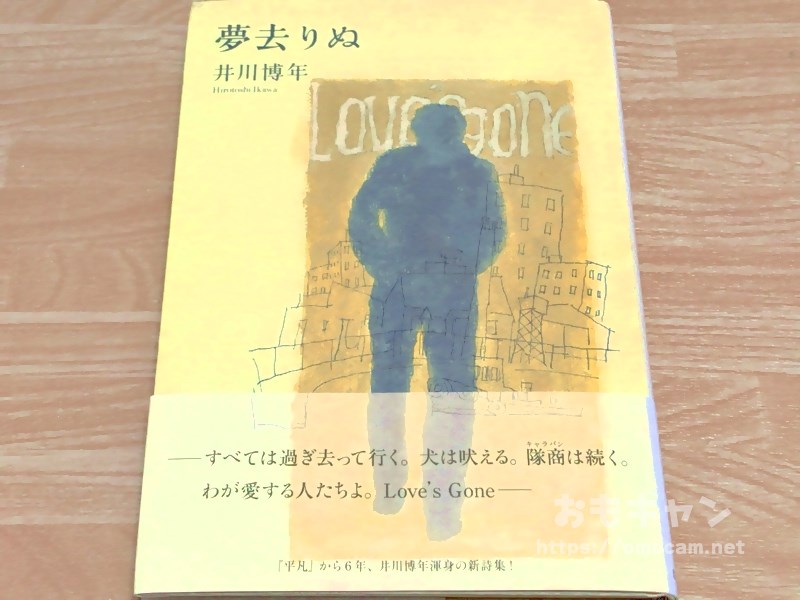どういうきっかけで井川博年さんの詩集を最初に手にしたのだったかはっきり覚えていないけれども、その最初に読んだ『幸福』という詩集の冒頭に置かれた、「出発は5分でできる」という一篇に好感を持ったことから、ぼくは井川さんの詩のファンになった。
その後、現代詩文庫の「井川博年詩集」を入手して読み、そしていま、この『夢去りぬ』を読み終えた。
2016年発行のこの詩集が、現時点で井川さんの一番新しい詩集なのではないかと思う。
井川さんの詩は平明であたたかく、率直な言葉の中にそこはかとないユーモアが感じられて親しみやすいのだけど、今回の詩集には、影を感じさせるようなところが多かった。
こころは
こんな明るい日は
外を歩きたくない
街を歩いていても
行き交うひとの笑顔を見ても
こころははずまないこんな明るい日に
外にでかけてみても
話しながら歩いている家族連れ
遊んでいる子供たちを見ても
こころはさみしいだけこんな外が明るい日は
ひとの知らない地下道を選び
涙を流しながら歩いてみよう
愛するひとを失った時のように
こころはかなしいから――わたしのこころは何処にいった
なにを見てもなにをしても
楽しかったあの頃のこころまだ夕暮れが明るい日は
茶色の鞄をさげて街に出よう
メトロに乗って買い物をして
小さな明かりの点いた家に戻り
誰もいなくてもこう言おう
「ただいま」と。こころは帰ってこないけど――
詩集『夢去りぬ』より
2006年の『幸福』から、「日暮れの町で」。
日常のひとこまや思い出を平易な言葉でうたって長く印象に残る、このような詩が井川博年さんの持ち味だと思う。
日暮れの町で
勤め帰りの町角で
アルバイト姿の娘を初めて見た。娘は店の制服を着て帽子を被り
私を見つけると澄まして
イラッシャイマセ
といった
濃い口紅が似合っていなかった
それを見るとなんだか
胸がいっぱいになった私はあわてて隠れるように
その場を離れ物陰から
娘と先輩が働く所を眺めた。
お客がきてケーキを頼むと
娘はぎこちなくでもきちんと包んで
アリガトウゴザイマス
といったはらはらしながら見ていた私も
合わせて
アリガトウゴザイマス
といっていた。
詩集『幸福』より
2001年の『そして、船は行く』から「春色母子風景」。
春色母子風景
なんでもいいからというと
うどんでいいという。
せっかくの外出でデパートで食べるのだから
うなぎにでもしたらというと
うなぎでいいという。
うなぎを時間をかけて食べ終わると
ほんとうはおだんごが食べたかったという。そこで外へ出て甘い物屋で
おだんごを食べる ここでは
九十歳の母は五十六歳の息子に
えんえんと話をする それも
自分のことだけ。
自分の置かれた境遇についてのことだけ。
息子の仕事のことは聞かない
聞いてもわからないから。
息子の家庭のことも少し聞くだけ
聞いても忘れてしまうから
もうそんなに会えないのに
もうそんなに時間はないのに
どうして二人はいつも
つまらない話ばかりするのだろう――。話終わると疲れて
バス停のベンチに座って居眠りをする。
それから老人ホームへ
ひとりでバスに乗って帰って行く。
詩集『そして、船は行く』より
井川さんの3冊の詩集から、発表年をさかのぼる形で詩を3篇引用した。
ぼくは彼の詩集以外に、井川さんその人の情報には触れたことはないのだけど、あくまで詩の内容に基づけば、娘のアルバイトをはらはらしながら見つめる詩を収録した『幸福』の時点で、井川さんは「春色母子風景」に描かれたお母さまを亡くされている。
そして「こんな明るい日は/外を歩きたくない」の詩を収めた『夢去りぬ』の時点では、そのお嬢さまも亡くされている。
井川さん自身の老いの意識も含め、『夢去りぬ』には死のにおいが濃い。
しかしそれでもこの人の詩のもつ明るさや優しさは、彼より何十年か遅く生まれて生きているぼくの心をも温め、やすらかなものにしてくれる。
「こころは帰ってこないけど――」と思うことが、ぼくにもやはりあるからだろう。